【PR】 ※本ページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。リンクから商品・サービスが購入・契約された場合、運営者に収益が還元されることがあります。
英国・サウサンプトン大学の研究者は、親による子どもの写真や動画のオンライン投稿(シェアレンティング)が、子どもの身元盗用や詐欺の被害リスクを高め得ると警鐘を鳴らしています。とりわけ近年の生成AIの普及は、画像・テキスト・音声のディープフェイクやプロフィール推定など、悪用の敷居を下げている点が懸念材料です。こうしたリスク認識を社会全体で高める必要があります。
なぜ子どもの写真投稿が危険なのか
- データの結合と特定化:投稿画像の背景・制服・名札・位置情報、キャプションや過去ポストが結び付くと、学校や生活圏などの特定につながりやすくなります。
- 生成AIによる偽造・なりすまし:顔画像や声が悪用され、ディープフェイクや声真似詐欺などの素材になり得ます。
- 消しにくい「デジタル足跡」:一度公開された情報は再共有やスクリーンショットで広がり、完全な削除が難しい場合があります。
- 研究の知見:サウサンプトン大学の学際プロジェクトは、シェアレンティングに起因する被害として、アイデンティティ関連犯罪やハラスメント等を確認し、注意喚起と対策資源の整備を進めています。
今注目すべき理由
- 被害の深刻さと不可逆性:未成年は自己管理が難しく、身元盗用や詐欺被害が長期化すると生活・心理面の影響が大きくなります。
- 「非公開」でも万能ではない:タグ付けや再共有で想定外に拡散するリスクがあり、公開範囲の限定だけでは不十分なことがあります。
- 社会的対応の必要性:学校でのデジタルリテラシー教育、プラットフォーム側の検知・抑止策、政策・ガイドライン整備など、複線的な取組みが求められます。
いますぐできる実践的チェックリスト
- 顔・制服・名札・自宅周辺が映る写真は避ける/モザイクやクロップで隠す。
- EXIFの位置情報オフ、キャプションに個人情報(学校名・行動予定・医療情報など)を書かない。
- 共有先は最小限にし、アルバムは期限付き・閲覧者限定のクローズド共有を使う。
- 子どもの年齢に応じて「同意」を確認し、嫌がる写真は投稿しない。
- 第三者が投稿した子どもの画像の削除要請手順を把握(各プラットフォームのヘルプセンター等)。
参考リンク
- BBC News:Sharenting—子どもの写真投稿がもたらす新たなリスク
- ProTechThem(University of Southampton):シェアレンティングのリスクと対策資源
- 同・The Study:研究の概要(調査規模・確認された被害類型)


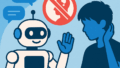
コメント